わたしは幼い頃から、絵をかくことが好きでした。
物心つく前から、鉛筆で広告の裏紙などに落書きをするのが好きだったそうです。
ときには、紙と鉛筆がないと怒り出すこともあったとか。
家族や親族には美術や芸術を学んだり、趣味としている人はほとんどいませんでした。
音楽や踊りに携わる人もいなかったようです。
そのような環境の下に育ったのですが、ある時から母方の祖父の存在が、絵をかくことに興味を深めていくきっかけになりました。
祖父はある日、脳卒中で倒れてから左半身に麻痺が残るようになり、要介護となりました。
それからしばらく経った後、祖父は短歌を好むようになり、色紙に短歌を書く際には、水彩で挿絵をかいていました。
祖父はわたしのために、挿絵付きの昔話を葉書にかいて送ってくれたことがありました。
当時、小学校低学年だったわたしは、毛筆で書かれた達筆な字を読むことができなかったし、その物語も難しい内容だったので、意味がわからなかったのですが、水彩でかかれた挿絵の印象だけはずっと憶えていました。
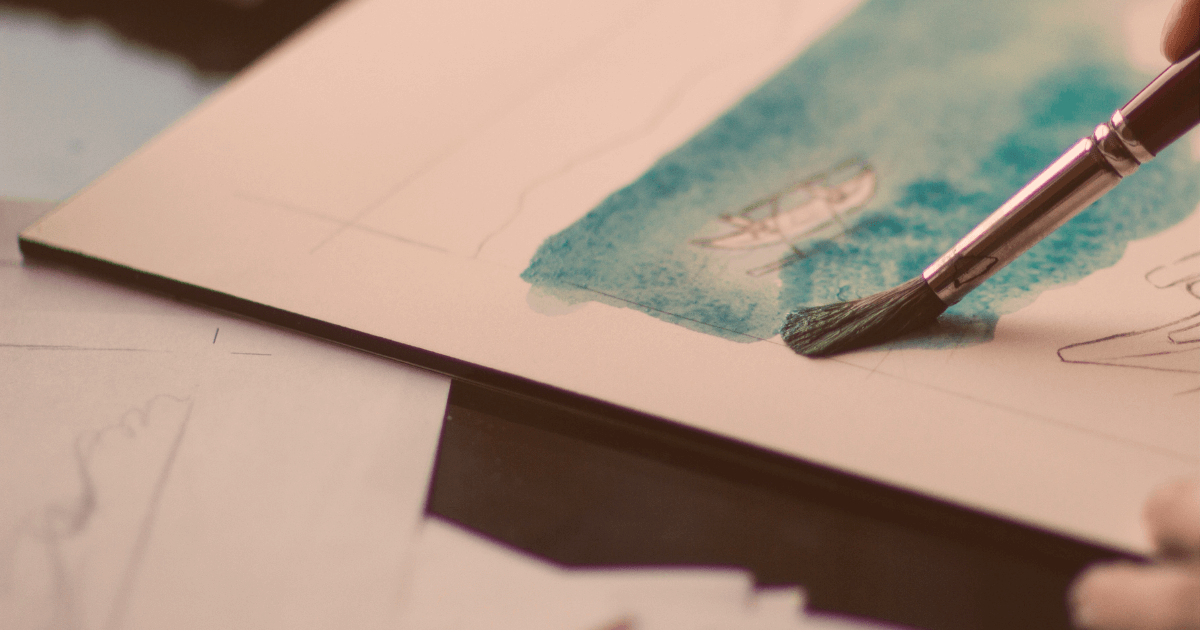
病弱で、人と接することが下手だったわたしを救ってくれたのは美術でした。
絵をかいているときや、新しく何かを作ろうと計画して動いているときに、度々訪れる感覚がありました。
それは、”無心になれるひととき”というものでした。
そのひとときが、日常のなかでの困難を一時的に忘れさせてくれたり、遣れば何でも出来るような気分にさせてくれたりしました。
それは、後にヨガを通じて瞑想を学んだときに体験した、”瞑想の状態”に近いものでした。
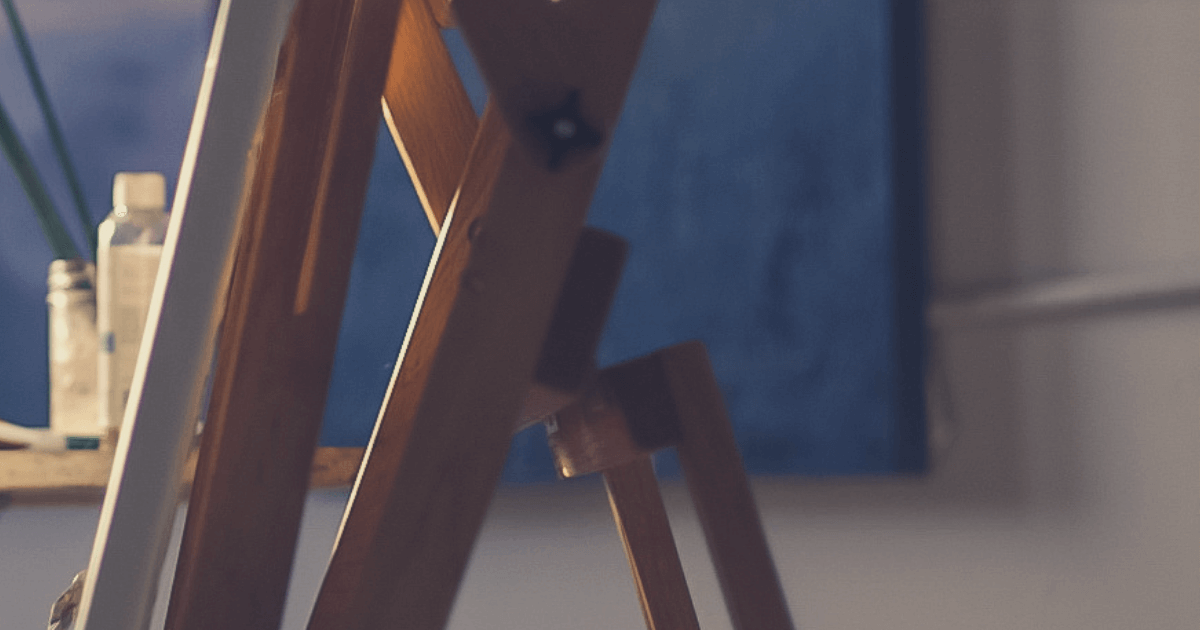
生きるために始め、自分を救うために続けた美術だったけれど、後に深手を負うことにもなりました。
実際に美術の世界で評価を得ながら続けていくことは、当時のわたしにとっては、あまりにも難しいことだったのです。
そのようなこともあったけれど・・・、未来とは本当にわからないものですね。
『人生にムダなことはない』
とはいいますが、本当にそうだと思います。
それどころか、時を経てから貴重な宝物に変わることさえあるようです。
つい最近のことになりますが、ふとしたきっかけが元で遠い昔の記憶を思い出すことがありました。
その記憶は、長い時を越えてわたしを癒し、希望をもたらしてくれたのでした。
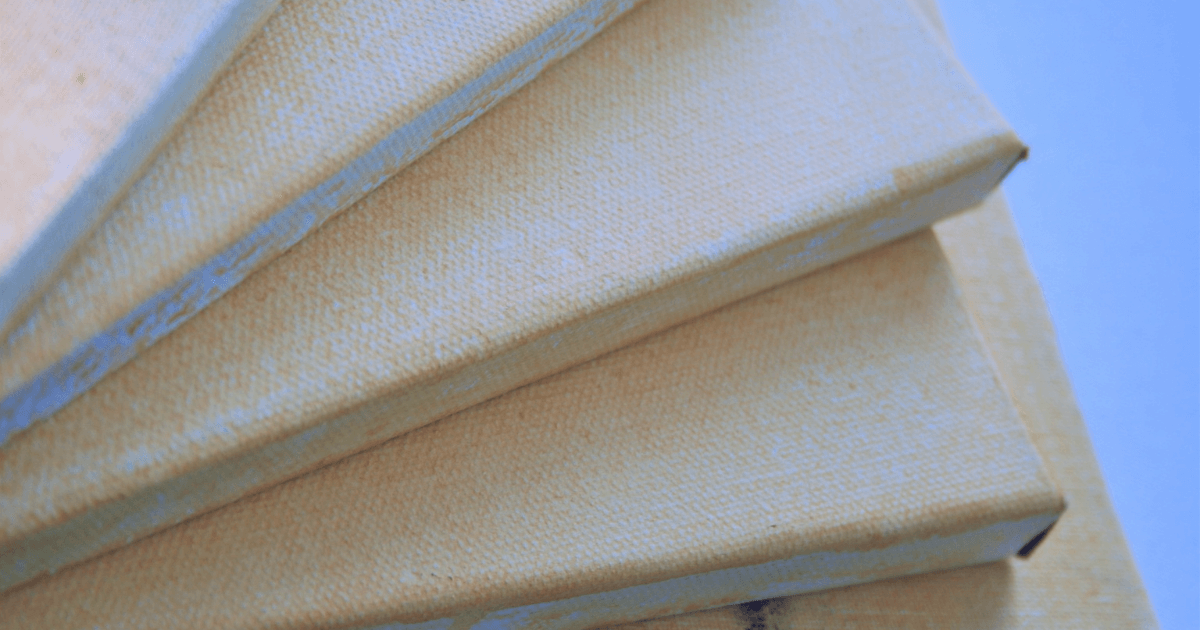
わたしは高校3年生の頃、油彩画を独学で学び始めました。
卒業式が近づいてきた頃、大好きだった人に似顔絵を贈りたいと思い、かきはじめました。
それは、F0号(キャンバスの規格で、人物型の最小サイズ。18×14cm)という、とても小さなキャンバスでしたが、2週間以上かかってしまいました。
そして、出来上がったものの、あちこち気になる箇所があったり、そして、何だか恥ずかしくなってしまって、結局本人には渡せませんでした。
懸命にかいたけれど、上手くかけたとは到底思えなかったのです。

その後、わたしは美大に進学したのですが、下宿に引っ越す際に、その絵を実家に置いていく気になれなくて、下宿に持ちこみました。
進学してからしばらくの間は、その人に会えない寂しさを噛みしめながら、その絵を見て向学心を奮い立たせていました。
それから数年後、ふとしたきっかけから、尊敬していた絵の先生にその絵を見ていただいたことがありました。
先生はその絵を目にすると、とても驚いたような様子で、その後もまじまじと見つめていらっしゃいました。
まだ、油彩を始めたばかりの若者が、充分に絵の具を使いこなせない状況でかいた絵です。
30年以上も油彩画を続けてこられた先生からすれば、その描写力や色使いなどは拙いものであることは明白でした。
長い沈黙の後、先生はささやくような穏やかな声で、
「これは・・・相当心を込めてかいたんだね。」
と、おっしゃいました。
そして、その後も眼鏡を外して、再びその絵を見つめていらっしゃいました。
当時のわたしは、その時に先生が何に驚いていらっしゃったのかがわかりませんでした。
そして、その後も、しばらくは何だか落ち着かない気持ちでいました。

似顔絵をかいていた時のこと、そしてそのとき抱いていた思い。
そしてあの日、絵の先生にそれを見ていただいた時のこと。
その後、それらの出来事がわたしにとって貴重な出来事だったと知ったのは、随分と年齢を重ねてからでした。
残念ながら、その似顔絵はいつの間にか手元から無くなってしまったのですが、それがどのような絵だったのかは、いまも記憶の中ではっきりと覚えています。
あの時、懸命になってかいていたその似顔絵は、わたしにとって原点そのものでした。
描写力や色づかいなどの技術的な面であれば、あの絵よりも上手くかくことはいくらでもできるだろうけれど、その背後にあったものを超えることはできないでしょう。
だからこそ、これからかいていく絵や作るものには、真心を込めて携わっていけると信じています。



コメント